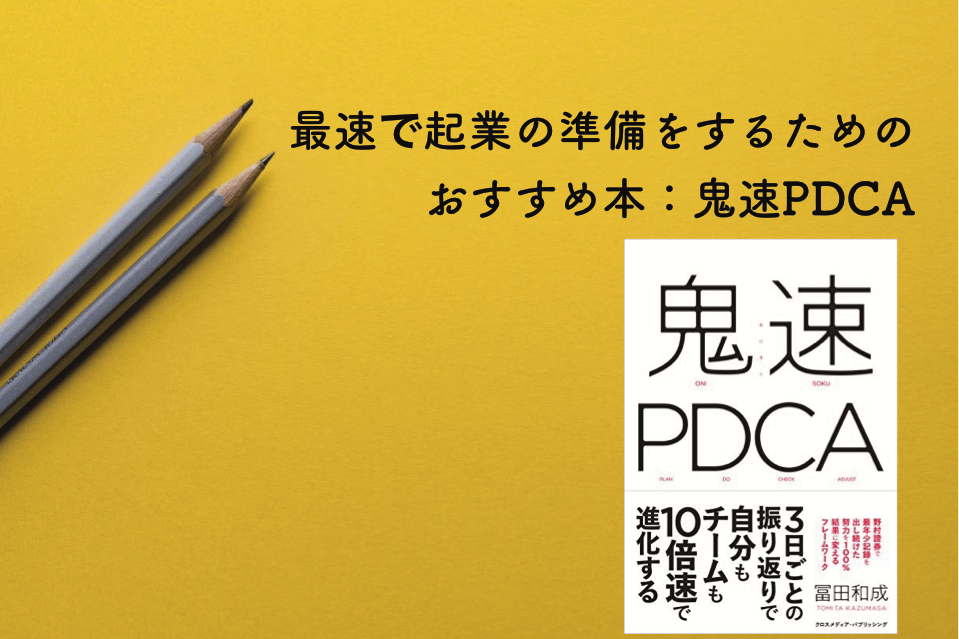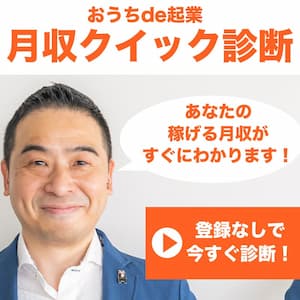ビジネスでは「スピード」が大事だとよく言われます。
Google創業者ラリーペイジもビジネスでのスピードの重要性について、こんなことを言っています。
失敗しても構わないが、失敗するなら早くしろ
またユニクロを世界的なブランドまで押し上げた柳井正さんも同じことを言っています。
スピードがない限り、商売をやって成功することはない。
だから失敗するのであれば、できるだけ早く失敗するほうがよい」「致命的にならない限り、失敗はしてもいいと思っていました。
やってみないと分からない。
行動してみる前に考えても無駄です。行動して考えて修正すればいい
この二人は小さな会社を創業し、グローバル企業にまで育てることに成功しています。
このこの二人が言っている共通点は「早く失敗する」です。
そこで今回は起業時になぜ「早く失敗する」必要があるのかを、本「鬼速PDCA」をご紹介しながら解説していきます。
この記事を読めば「鬼速PDCA」の本に書いてあるポイントがわかるだけでなく、Google創業者ラリーペイジや柳井正さんが言っている「早く失敗する」ことがどういうことなのかがわかります。
そしてあなたの中で最速で起業の準備するにはどうすればいいのかが明確になります。
今の時代に起業するからこそPDCAが必要になる
「PDCA」と聞くと「もう古い」「やったけど難しい」「もう知ってる」と思う方も多いかもしれません。
しかし、本当にそうでしょうか?
もしかしたら「もう古い」「やったけど難しい」「もう知っている」と思う方は下記のような誤解があるかもしれません。
PDCAはもう古い?
新しいビジネス手法を取り入れるためにもPDCAは必要になります。
つまりPDCAのスキルは他の手法の根底となるので、古いや新しいということではなく、ビジネスをやっていくためのベースになるスキルです。
PDCAは難しい?
PDCAが難しくなる原因は「PLAN(計画)」をしっかり立てていない時です。
「PLAN(計画)」をしっかりできればそう難しいものではありません。
PDCAはもう知ってる?
もしかしたら簡単なPDCAを回しただけで、知っていると思っているかもしれません。
私が考えるにビジネス環境の変化が激しく、いろんな商品やサービスが溢れている時代に起業を成功させるには「PDCA」を使いこなす必要があり、今の時代だからこそもう一度「PDCA」をしっかり身につける必要があると考えています。
そして、起業とPDCAはとても相性がいいのです。
起業とPDCAは相性がいい
起業とPDCAの相性がいいポイントを解説します。
モノやサービスの商品が溢れている中で、起業したり新規事業を立ち上げるときには、「差別性=独自のウリ」を打ち出す必要があります。
しかし「差別性=独自のウリ」を生み出すのは簡単ではありません。
一番効率的でスピードよく「差別性=独自のウリ」を生み出す方法は
- 素早くビジネスモデルの仮説を立てる
- 仮説で立てたビジネスモデルを検証する
- 検証結果から学習した内容をビジネスモデルに取り入れる
この1〜3を繰り返すことです。
この「仮説を立てて検証し学習するサイクル」はまさに「P(計画)D(実行)C(検証)A(調整)」と一致するので、起業とPDCAはとても相性がいいのです。
ただ気をつけなければいけないのが、PDCAをしっかり回していくにはそれを継続する仕組みを自分なりに作る必要があります。
この継続する仕組みを作る時に参考になるのが、今回紹介する「鬼速PDCA」です。
起業準備でPDCAを使う事例
例えば、起業の準備段階で「商品を作る」時にPDCAがどう当てはまるかを考えてみましょう。
商品を作るプロセスは次の通りです。
- 「アイデア」を生み出す
- その「アイデア」が誰にとって役に立つのかを仮説で考える
- 仮説を元に【見込み客にとって】必要な機能を洗い出す
- 試作品をつくる
- 見込み客に試作品として提供する
- 見込み客からのフィードバックを受ける
- フィードバックから学習し、「1」に戻る
このプロセスとPDCAサイクルを組み合わせると
1〜3は「P(計画)」
4〜5は「D(実行)」
6は「C(検証)」
7は「A(調整もしくは改善)」
となり、このPDCAを回すことで、売れる商品を生み出すことができます。
鬼速PDCAの出版された背景
ここで「鬼速PDCA」が出版された背景にも少し触れておきます。
この本の著者は野村証券時代にPDCAに取り組み、独自にどうしたらPDCAをうまく回していけるかを追求してきました。
そして野村証券から独立し株式会社ZUUというIT技術を使った新たな金融サービスを提供する会社を立ち上げ、今度は自分だけではなく他の人にPDCAをどう伝えるかを試行錯誤されてきました。
その中で独自のやり方を開発して、そのやり方を今度は社内文化として残すために、今までの独自のPDCAのやり方を体系化するためにこの本を執筆されたそうです。
なので、学術的な本ではなく、この本は「実用書」として読むことができます。
鬼速PDCAを読んでみての感想
私はこの本のタイトル「鬼速PDCA」を見たとき気にはなりましたが、タイトルから軽い内容が書いてある印象を受けたり、PDCAはもう知っていると思っていたので購入しませんでした。
それから1年後、「やり抜く力 -GRIT(グリット)」を読んで、もっと実行力を身に付けたいと思っていたときに、また本屋で「鬼速PDCA」に出会いました。
以前から気にはなっている本なので、一度は読んでみるかという軽い気持ちで読み始めたのです。
そんな軽い気持ちで読み始めたのですが、読み進めるとPDCAの各ステップがかなり詳細に解説してあり、自分はここまで明確にPDCAを回していなかったことに気づき真剣に読み進めました。
そして、今は売上アップやビジネスの仕組みづくりのために本書で学んだことを実践しています。
鬼速PDCAの違い
今までのPDCAと鬼速PDCAの違い
今までのPDCAはどちらかというと「マネジメント」する時に利用するフレームワークと考えられていることが多いと思います。
しかし、本書を読めばPDCAは「前進を続けるためのフレームワーク」というイメージに切り替わり、その前進するスピードを実感できることができ、モチベーションが上がり、さらにPDCAを回すスピードが加速します。
「鬼速PDCA」の特徴
この「鬼速PDCA」はPDCAを実践しやすい解説があったり、明日からすぐ実行できるノウハウが各ステップごとに豊富に書いてあるのが特徴です。
例えば
PLAN(計画)
- PDCAがうまく使いこなせるかはPLAN(計画)が5割!そのPLAN(計画)を立てる細かいステップ
- PLANの中でしっかり課題設定、解決策をつくる方法
DO(実行)
- DOの事をの優先順位をつける方法
- DOを具体的なアクションまで落とし込む方法
CHEK(検証)
- CHEK(検証)で必ず検証する項目について
- CHEK(検証)でうまくいってない場合の要因分析する方法
ADJUST(調整)
- 一般的にはACTION(改善)とされているが、本書ではADJUST(調整)とされている
- ADJUST(調整)は改善だけでなく、良いところも伸ばす伸長案も踏まえている
などPDCAの各ステップについてのノウハウがたくさん掲載されています。
まとめ
冒頭のGoogle創業者ラリーペイジや柳井さんが言っている「早く失敗する」というのは、ただ失敗するだけでなく「失敗した経験から成功の種を見つけ活かす」このサイクルを早めることと言っているのです。
つまり具体的にはPDCAのサイクルを早く回すということです。
このPDCAサイクルが早く回ることで、ビジネスはどんどん成長していきます。
そしてこの「鬼速PDCA」ではPDCAのサイクルを回すポイントやテクニックを詳しく解説してあります。
PDCAに不慣れな方のために「初級編」と「応用編」として分けてあったり、巻末には気軽にPDCAを体験するための「10分間PDCAワーク」や実際に著者の会社で使用しているPDCA補助ツールがダウンロードできます
他のPDCA補助ツールとして
・工数棚卸しシート
・鬼速進捗管理シート
・なるほどシート
・ルーチンチェックシート
などもダウンロードできます。
このツールだけでも最速で起業の準備をする時に役に立ちますので、下記のリンクからぜひ読んでみてください。
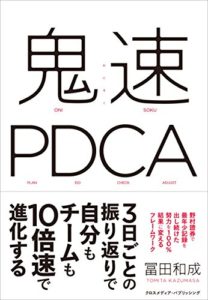
商品:鬼速PDCA
著者:冨田 和成
価格:定価1,598円